「遍路用具を作っている人って、歩き遍路したことあるの ? 」、「遍路用品販売店の人達って、歩き遍路したことあるの ? 」、歩き始めて以来こんな疑問を抱いていました。 ⇒ 作っている人にも、販売している人達の中にも、どうやら歩き遍路の体験者はいないように思います。
「私は、何でも知っているのよ」 みたいな風情で遍路用具を売っている店員達の実体は、全くのズブの素人さんです。 自動車やバス等での札所巡りをされたことがあるとしても、歩き遍路の経験などは全く無い人達です。 歩き遍路のことを何も知らないから、疑問を感じ得るだけの体験や知識もないから、使い便利の悪い用具なども平気で、しかも親切そうに売りつけているのです。 ⇒ 遍路用品・道具の改良改善や手作り・道具類の自作をお奨めします。
| ☆ 歩き遍路さんの使用する杖は、急な上り下りの遍路 道で足や膝への荷重負担を軽減する道具であり、スリップを予防し、身体を押し上げる支柱として、そして犬などへの防具としての機能を果たしてくれる必携の
遍路用具です。 杖に求められる要件は、①重力(重量×加速度×段差)を支え得る強度、②両手ですがり易い長さ、③持ち運びの負担にならない軽さ、④遍路用具としての外観を備える必要があります。 *現在、歩き遍路さん用に適した杖を販売している店舗はありませんので、ご自分で調達・自作することをお奨めします。→ 自分自身で作る杖は しっくりと我が身に馴染みますし、心強く安心感が増します。 *経験上、杖はご自分の「身長の長さ(身の丈)又は7~8cm位短い長さの範囲の杖」が使い便利も良いように思います。 なお、市販の金剛杖は自動車のトランクに収納できるサイズ(130cm)で販売されています。⇔自動車利用の札所巡り用グッズです。 *【上の写真の杖】は私の現用のへんろ杖(金剛杖)です。 〇一番上は、市販されている杖の材料です。24mm×24mm×1800mmの柾目材でホームセンター等で簡単に入手できます。販売されている金剛杖と同じ素材です。 ⇒*貴方の身長に合った長さ(身の丈又は7~8cm短め)に切れば完成です。*因みに私の伸長は168cmです。 〇二番目と三番目は市販されている杖の材料で自作した杖です。二番目は155cm、三番目は146cmの長さです。 〇四番目・五番目は自然木、杉間伐材の先端部分で作りました。乾燥させた芯材ですので強くて軽いです。しっくりと馴染みます。四番目は160cm、五番目は159cmの長さです。*なお、自分の使用する杖には、接地部分にキャップを被せ摩耗対策としています。 〇六番目と七番目は最高級の金剛杖です。漆系塗装に金文字彫刻した特注杖で、それなりのお値段です。使い易く、最高の金剛杖です。六番目(黒杖)は160cm、七番目(朱杖)は154cmです。なお、接地部分のキャップは特注品で使い具合は大変に良好です。 〇八番目・九番目・十番目の杖は一般に市販されている金剛杖で長さは130cm、昭和三十年代から製造され、一般に販売されはじめました。 *高身長の方々には、実使用上では少し短く感じるだろうと思います。 *九番目の杖の材質は桐材です。←少し、軽すぎます。 〇十一番目の杖は先達杖(朱・丸杖)で釈丈先端まで162cm。→重くて、滑りやすく、実用性に欠けます。見た目(外見)に重きを置いて作られています。 ☆金剛杖を使わずに「登山用ポール」で代替するのも OK です。長尺(130cm~)のポールがお奨めですし、二本持参をお奨めします。 ≪参考≫ 江戸時代の書物に記されているお遍路さんの杖は「竹杖」です。 |
| ○へんろ笠(竹笠・檜笠)は現物を確認してから購入しましょう。 販売されているへんろ笠の品質は、良好とは判定できません。 粗雑な部品や部材の取付けに手抜きも感じられる商品が陳列・販売されているように思われます。 手抜きの具合から、はたして日本で作られているか否か、を疑います。 →中国製などは粗悪品が多いので注意すること。 * へんろ笠を購入される場合は、まず現物をよくチェックしてからお選びください。 ○へんろ笠(竹笠・檜笠)を入手したら、笠紐を必ず付け換えましょう。 A、適当な紐(60cm位)で、耳が収まる程度の長さの輪を五徳の左右の耳の位置に取り付けます。→①② B、左耳、右耳の紐の輪を通して、あごの下に掛け、唇の下側で結べる長さの紐を取り付けます。 この時、一方を長くして唇の下側で結び易いような長さに調整して取り付けてください。→③ 紐の長さは90cmぐらいが適当と思います。⇒右図参照。 →私は白色の靴紐(90cm)を使っています。紐の先端が解れず最適です。 C、左耳の輪①と③の紐を④で結べば使い便利が良いです。 D、笠と五徳⑥との取付がゆるい場合、結束バンド(極小)で補強すれば簡単でしっかりと取り付けできます。→⑤ E、五徳と頭皮が接する部分⑥に布や包帯を巻けば頭皮に優しく、しっくりと馴染みます。 *笠紐の取り換えと結束バンドでの補強により、風にも強いへんろ笠になります。→⑤ 改良費用は100円程度で済みます。 *へんろ笠は、梵字が正面を向くように被ります。 紐の取り付け位置に注意してください。 *ご自分専用のマークを付けておけば、他人様の笠との混乱が無くなります。 |
 |
私はリュックの中に、濡れた雨具や生乾きの衣類を収納することに抵抗感があります。 他の荷物が湿ったり濡れたりするのが嫌だからです。 そこでリュックの外側に保管する方法はないものか? と考え思い付いたのが左写真のような洗濯ネットの利用です。 使用してみると、知らぬ間に濡れた雨具なども乾きますし、歩行に何の影響も生じません。 また、洗濯ネットは風呂上がりに汗で汚れた衣類を入れておけば、移動中に靴下の片方などを紛失する懸念もなく、そのままの状態で洗濯もできます。 洗濯ネットの適当な位置に吊り下げ紐を取り付けておき、リュックのワンタッチジョイントに引っ掛ければ完了です。 軽くて安くて簡単です。 歩き遍路専用の物干し場を工夫してみてください。 ちなみに、コストは110円でした。 *ワンタッチジョイントの代わりに洗濯用クリップを取り付けて使っている方もいます。 |
||
| 線香やローソクは持ち運びの途中で折れたりバラケたりし易く、消費量も結構多いことから、取り扱いやすい道具はないか?と誰もが感じていることです。 【右写真】は、紐などを取換え、部品等を取付け改良した私の使用している線香・ローソク入れです。 改良箇所は ①吊り下げ紐を取り換えます。 ②取り換えた新しい紐にはコードストッパーを取り付けます。これは、持ち運び中にフタが開かないようにするためです。 ③ライターとセットになるように工夫します。 ④線香とローソクがワンケースで収納できるので楽です。ローソクは二段に収納しています。 ⑤予備のライターを持参してください。 ⑥線香やローソクの補充が必要となります。その場合、コンビニ等で調達可能ですし、良品を割安で入手できます。 ⇒ 札所寺院でも販売していますが、価格は随分と張ります。 |
 |
||
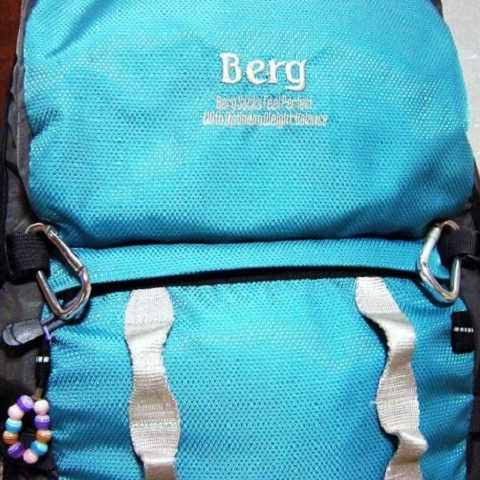 |
*ジョイントの取り付け*リュックの背、外側はフリーに利用できるスペースです。このスペースを有効活用するた め、適当な箇所にワンタッチジョイントを取り付け(左の上側写真)ます。そのジョイントにへんろ笠の紐を吊り下げた例(左の下側写真)です。コンビニのレ ジ袋を引っ掛けるだけで、便利な収納スペースも臨機応変に確保できます。 *ワンタッチジョイントの代わりに洗濯クリップを取り付けている方も見かけます。ご自分に合ったやり方を工夫してください。 |
*和手拭の「ほつれ」予防*和手拭は薄くてかさ張らず、使い便利の良い物です。しかし、和手拭の端が解れる欠点がありますので、使用前に端を三つ折りにしてミシンで縫っておけばしっかりとして解れることもありません。 *和手拭は頭部に巻き、タオルは首にかける形が便利です。 般若心経などの文字柄手拭いが案外とお似合いです。 |
||
 |
||||
昔と変わらぬ本物の「歩き遍路」に![]() 関心のある方はこちらをご覧ください。⇒ お四国センター 直心(じきしん)
関心のある方はこちらをご覧ください。⇒ お四国センター 直心(じきしん)
Copyright (C) 2009 Eiji.shirahama. All Rights Reserved.